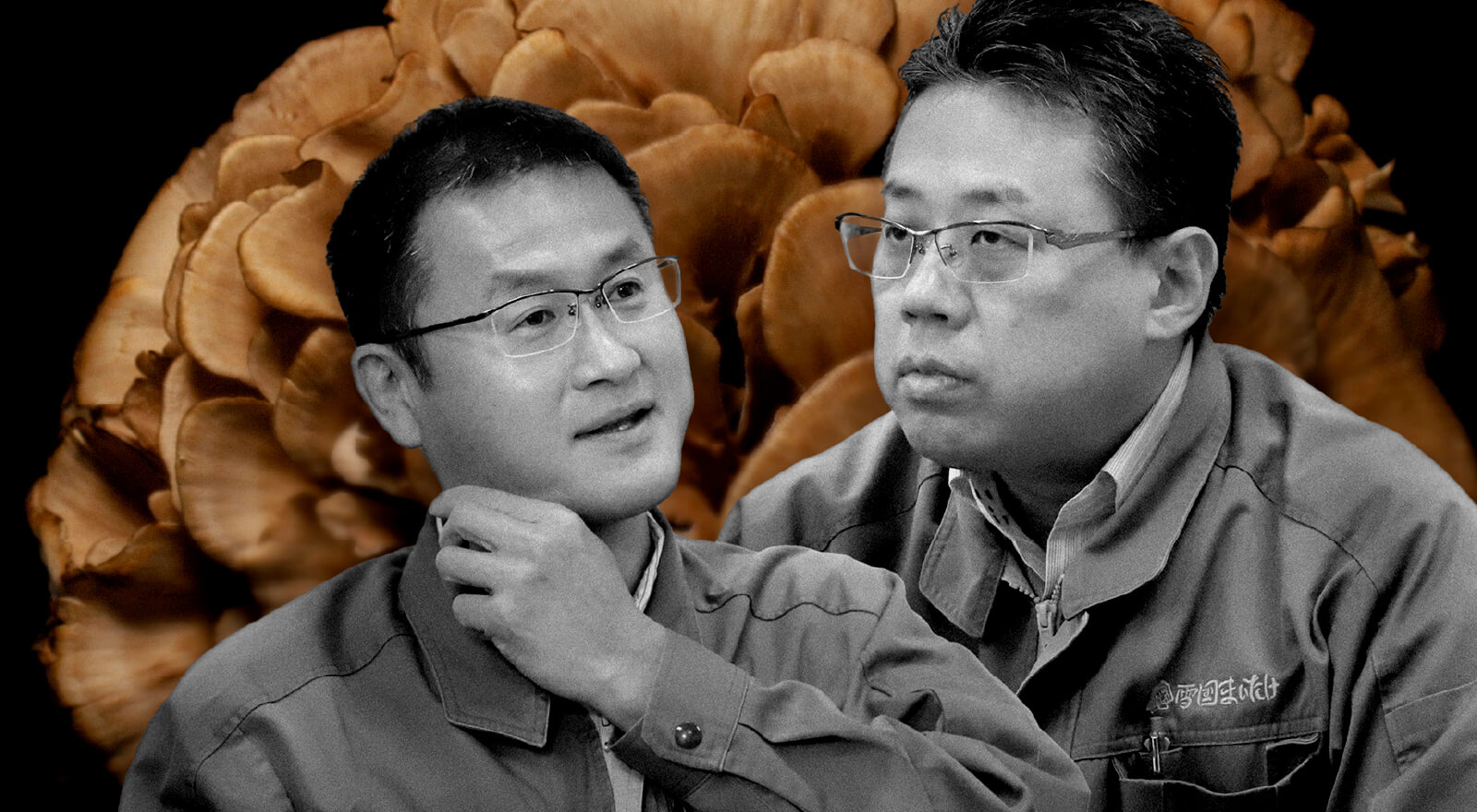極める。
極める。

希少で栄養価の高い舞茸を、量産し続けてきた雪国まいたけ。1995年には、従来品より更に優れた菌株の開発に着手する。以来、試行錯誤し、20年。
2015年には数々の弱点を克服した、念願の「極(きわみ)」菌を生み出した。自社の開発菌に挑んだ開発者たちが味わった、数々の挫折や葛藤、喜びとは−?

1980年代、日本はグルメブームに沸いた。フランス料理やエスニック料理、1990年を前後したバブル景気の時代には、熱狂的なイタ飯ブームの到来。そうした多様な食の流行を経て、日本人の食生活は豊かに様変わりした。舞茸も定番の鍋物から、国籍やジャンルを超えたメニューに使われていく。
食材としての可能性が、大いに広がった。
そんな最中の1991年。きのこ産業のパイオニアとして生産技術を確立するため、雪国まいたけは研究開発室を新設した。当時、雪国まいたけで使用していたのは、種菌メーカーから購入する「菌株A」だった。舞茸産業の歴史はこの菌から始まったと言われるほど、食味の良い優秀な菌株である。ただ、煮込むと料理の見栄えを損ねる黒い煮汁が出てしまい、料理によっては歯応えが物足りないなどの課題があった。研究室ではより良い舞茸を育てるため技術開発を続けたが、その弱点はなかなか克服できずにいた。
1995年、雪国まいたけの上層部は思い切った方向転換を示す。
「自社で、舞茸の菌株を開発する」経営基盤確立のためにも、他社の菌に頼らず、
独自の魅力ある商品を提供したい
その思いは熱かったが、自社による菌株の研究開発は初めてのこと。未開の地への、手探りの旅の始まりだった。
研究開発部で、自社菌株の開発を担ったのは小島陽光である。
「カサの色を薄めに抑えることは、さほど難しくはなかった」
と、小島が開発時を振り返った。製造部で3年にわたり、舞茸の生産に携わったことのある小島は、菌株Aの〝作りづらさ〟を実感していた。例えば、外気温が高い夏と、氷点下にまでなる冬とでは、同じ温度に設定したとしてもきのこの育ち方が違う。春から秋はきれいな球体になるが、冬場は理想の形にならない場面が多く、良品が収穫できない。供給量が目に見えて下がる日もあった。
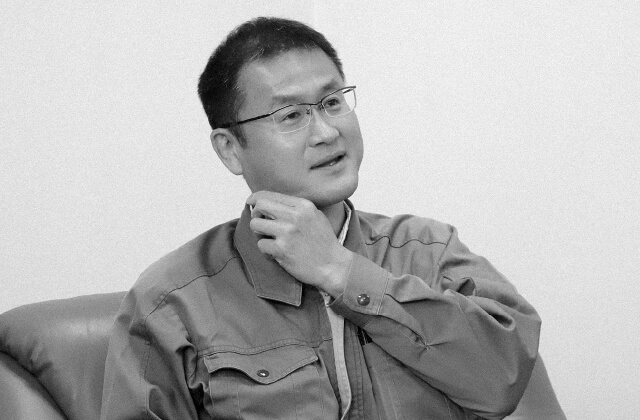

菌株というのはトータルで良くないとだめ。煮汁の色が薄く味が良くても、日持ちが悪いとか、年間を通して安定した品質で作れないものは論外でした。
研究開発部長小島 陽光
自社菌株開発のため小島がまず始めたのは、品種改良を行うための素材(舞茸)集めだ。舞茸を求めて地元六日町や十日町市の山中、または山形県・福島県との県境をまたぐ飯豊連峰などへ出向く。土地の山名人を頼って山へ入り、舞茸を探して歩いたり、露店商が出る山あいの地域を訪ねて舞茸を購入した。売っていなければ「採れたら教えて」と、名刺を渡す。小島は休日を利用して各地を回り、車中泊をしながら舞茸の姿を追った。秋になり、露店で天然舞茸が売られていると聞くと、気がはやる。手に入れて帰宅するのは日の暮れた日曜の夜、という日も珍しくはなかった。
舞茸探しは何年にもわたった。初めは小島1人だったが、その後、研究室の後輩が加わり、3~4人で休日の探索を行った。山の名人でさえも、見つけたら小躍りするほど喜ぶという舞茸である。大きなミズナラの木の根元に出ると言われているが、そう簡単には見つからない。小島が実際、数年のあいだに山で採れたのは3回という。
「意外にも民家のそばにあったんですよ」
と声を張る小島から、当時の興奮が伝わってくる。

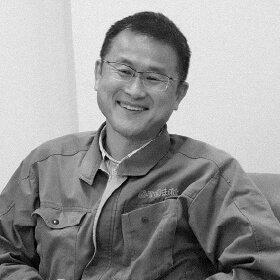
苦労して集めた舞茸は、交配して育種を行う。目的にあった菌を選抜するには、多様な遺伝資源を持つ素材を、いかに揃えるかが重要だ。できるだけ多くの野生株を集め、舞茸の1つ1つを写真に撮り、番号を付け、組織分離を行って培地(土台)に植えた。研究開発部では育てた舞茸の形や味、色、日持ち等のデータを蓄積していく。
舞茸の菌株作りはまさに、宝を探り当てる感覚。私自身、そういう作業は好きでしたから、やっていて楽しかった。ただ、相手は生き物です。土日だからといって生長を休まない。僕らも毎日、毎日、発生室に入って〝きのこ漬け〟です。あるとき終業後に出かけた先で、見知らぬ人から 『あなた、雪国まいたけの人でしょう』と。私の身体にも、まいたけの香りが染みついていたんです。


自社菌株は、2000年に完成をみる。名前は「Y10M」(雪国舞10号の意)。1995年に着手して、丸5年が経っていた。研究開発部では5年のあいだに、1000株以上の大掛かりな交配を行っている。膨大な株の中から、理想に近いものを絞りに絞って選んだY10M。生産工場でも1年にわたる試験栽培を行い、安定した生産が可能との結果を得た。社内会議でのプレゼン用に、小島は自ら炊き込みご飯や舞茸チャーハンを作って持参し、上司に託した。カサの色を薄めに仕上げたことで煮汁も薄くなり、これまでにはないシャキシャキした歯ごたえが自慢の舞茸だ。小島は自信を持って、上司からの吉報を待った。しかし、結果は予想外の返事。上層部の反応はいま一つで、「主力品種にはできない」という。その理由は食味ではなく、「生産性の低さ」だった。菌株Aでは一株800グラム以上採れたのに対して、Y10Mは700グラムほど。食感や見栄えは良いがコストがかかるということで、菌株Aの代替品にはならなかった。小島は落胆した。しかし、仕事は終わったわけではない。「また次の菌株を」と、頭を切り替えた。
その後、Y10Mは食味の良さが認められ、2004年にはプレミアム品「シャキシャキまいたけ」としてデビューした。だが高価格帯の商品ということもあり、需要が少なく生産量も上がらない。高品質な食材を求める、都心の蕎麦店にのみ卸すような販売が続いた。当時、生産本部栽培技術部でY10Mの栽培管理に携わった行方景久が言う。


最も少ない時には、週に1度、200株を収穫する程度。本当に微々たるものでした。でも、このY10Mは弾力があって歯応えが良く、年間安定してカサが綺麗に丸くなる。確かに小振りではあるが、弾力があることで崩れにくく廃棄する部分も少ない。結果的に生産性を上げる、優れた菌株でした。
常務執行役員 生産本部長行方 景久
一時は営業から「売先がない」との声が上がり、Y10Mの生産中止が検討されたこともあった。しかし行方の上司である当時の生産本部長も、Y10Mの品質を大いに認めていた。「止めるには惜しい」――生産現場の勝手な判断にはなったが、Y10Mの量産試験は規模を縮小せず継続する決断をした。

「週に1度しか生産しない舞茸は、思いのほか手がかかった」
と証言するのは、試験栽培に携わっていた向川戸克徳である。


Y10Mを菌株Aと同じ条件で培養すると、きのことしては発生してほしくない物質が出てしまう。そこでY10M独自の培養条件や、管理技術が用いられました。少量だからこそ作りにくい要因が揃ってしまっていた。
第1バイオセンター係長向川戸 克徳
現場の手を煩わせたY10Mだったが、品質が良いのは誰もが認めるところ。
そこでスペースを広げて量産試験を行うようにしたところ、変化があった。向川戸が続ける。


栽培量を増やすにつれて、良いものができるようになったんです。菌株Aの課題だった冬の品質が、Y10Mだと良品率95%まで上がった。目を見張る数値でした。
自社の菌株開発が足踏みをする一方で、進められていた研究がある。菌株Aの生産性を上げるための、培地の見直しだ。2012年には、菌株Aの特性に合わせた新培地が完成する。舞茸は、培地の原料や栽培技術の組み合わせによって、生育状態が変化する。菌株AとY10Mも、それぞれの培地組成は異なっていた。生産現場を知る川瀬亨が、原料の配合調整に関わっていた当時の苦労を語る。


第1バイオセンター長川瀬 亨
そこで現場では大胆にも、
菌株Aの新培地をY10Mにも使ってしまう。
菌株の種類ごとに培地の栄養量などを変えて配合しますが、製造ラインの設定を小規模生産のY10Mのために直さなければいけない。1日に2万個の製造に関わる中で、それはかなり面倒な作業でした。

第1バイオセンター長川瀬 亨
そこで現場では大胆にも、
菌株Aの新培地をY10Mにも使ってしまう。


当時の工場長が、『勝手にやって、上からだいぶ怒られた』と。試験的な試みでしたが、現場の大変さを何とかしたい思いだったのでしょう。
川瀬が上司を慮(おもんばか)った。ところが、である。この新培地が、予想を超えた働きを見せた。菌株AよりもY10Mとの相性に優れ、Y10Mの収量がぐっと上がったのだ。これを追い風に、現場では更なる生産技術の改良を実施。2014年にY10Mは、1株800グラムを超えた。菌株Aと肩を並べるまでに生長したY10Mに、現場は大いに湧いた。時を同じくして、雪国まいたけの経営層が一新。これもY10Mに優位に働いた。「なぜ、こんなに良いものを放っておくのだ」。経営層からの強い後押しで、菌株Aの舞茸はすべて、Y10Mに切り替えられることになった。2015年8月、Y10Mによる新ブランド「雪国まいたけ極(きわみ)」がデビュー。研究開発から20年目の、晴れの日であった。


これら一連の流れを見てきた行方は現在、常務執行役員 生産本部長である。「極」が辿った長い歩みを、行方がこう評した。
新経営陣は異業種から来た方々で、舞茸業界は初めて。その曇りのない視点で極菌(Y10M)を選んだ。生産性より、歯ごたえや味わいを重視し惚れ込んでくれたことは、細々とでも作り続けてきた現場にとって、本当に嬉しいことでした。また現場で極菌を新培地に移植した動機は、『培地が一緒なら楽だし、同じもので育てたらどうなるか?』というものだったでしょう。量産試験のスペースを徐々に広げたのも同様で、製造現場の『面倒くさい』を無くすことは重要であり、それが結果的に極菌の価値を高めたのです。

「雪国まいたけ極」は、その後も培地の改良や栽培環境の条件を変え、品質と生産性を上げている。現在では一株900グラムを超え、堂々たる風格だ。そのしなやかで美しいカサがパックされ、売り場に整然と並べられる。それを見て、開発者の小島も目を細めているという。